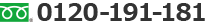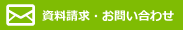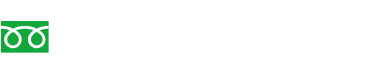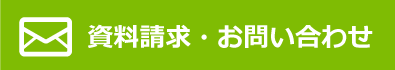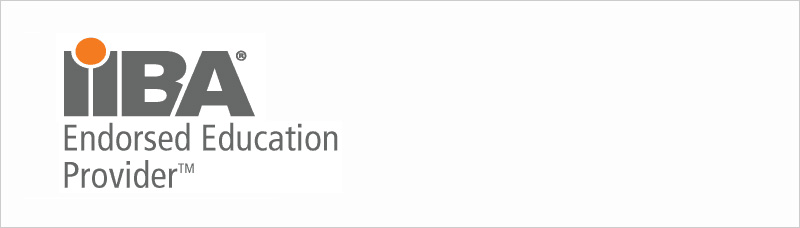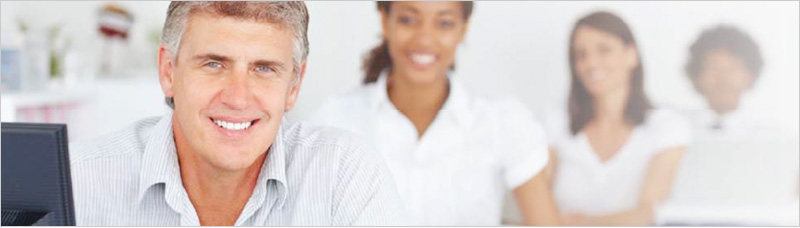2025.07.22
【責任編集】ラーニング・ツリー
デザインシンキングについての考察(2)
今回は、デザインシンキング、DX、ビジネスアナリシスについて、それぞれのフレームワークの共通点と関係性を考察してみます。
当社は、デザインシンキングの他、DX推進を支援するコースとして、ビジネスアナリシス関連講座の受講を推奨しております。
基礎を学ぶ入門編から、BPR、要件定義(ユーザ要件、システム要件、データ要件)、ケーススタディなど、実戦的な演習を含む講座を提供しております。
・DXについて
2018年に経産省が「デジタルトランスフォーメーション(DX)を推進するためのガイドライン」を発表しました。その後、2022年に改訂版となる「デジタルガバナンス・コード2.0」が策定され、DXは、「企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品、サービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること」と定義されました。
要するに、デジタル技術を活用した顧客視点のビジネス価値創出がDXのゴールと言えます。
・DXを支えるデザインシンキング
デザインシンキングは、その特徴からDXとの親和性が高いと考えられます。提供物の先にあるユーザを常に見据えてプロセスを実行することについて、ともに人間を中心に据えることが共通点です。
デザインシンキングをDXのフレームワークにうまく取り入れることで、新たな価値づくりが促進されると考えられます。
・DX推進を支援するビジネスアナリシス
新たな事業企画やシステム近代化など、ユーザを含んだステークホルダの要望を的確にくみ取りながら、プロジェクト全体を俯瞰しつつ、潜在ニーズを要件に落と込んで、本質的なニーズを付加価値に転換し、サービスや製品の展開やシステム設計開発に適用することがビジネスアナリシスの役割です。ステークホルダとの関わり方と要件定義は特に重要となります。
・まとめ
デザインシンキング、DX、ビジネスアナリシスは、重なり合う領域も多く、これらフレームワークを深く理解してビジネスプロセスに取り入れて活用することで、新たな価値創造への相乗効果が期待できます。
いずれも人間を中心に据えていることが共通の特徴です。
現在のビジネス環境では、個々のフレームワークを実践的に体験する段階から一歩進んで、目に見える成果を出せる組織づくりに不可欠な構成要素として、これらフレームワークの位置づけと役割も変わりつつあるようです。