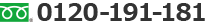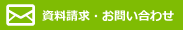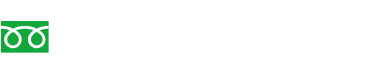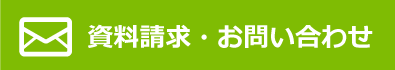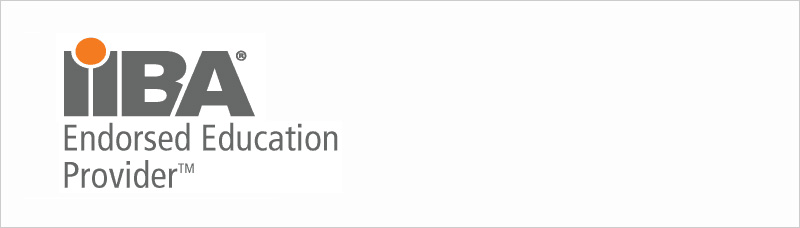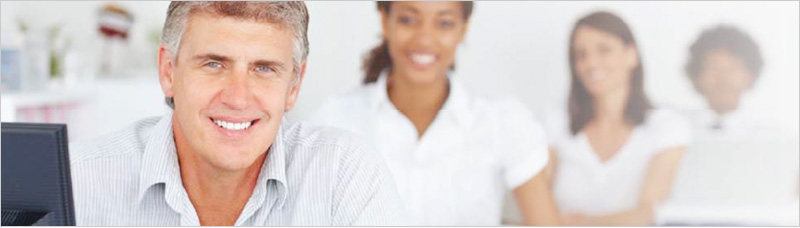2025.09.16
【責任編集】ラーニング・ツリー
企業がすべき人材育成とAI
生成AIの普及は、これまでのテクノロジー変化の中でも際立った速さと広がりを見せています。
ChatGPTの登場から数年で、AIはプログラミング補助、文章生成、顧客対応など多様な業務に入り込み、特にIT業界では「AIなしでは事業継続すら難しい」という危機感が共有されつつあります。
単なる業務効率化の道具ではなく、AIは事業の前提条件となりつつあるのです。この現実に直面する中で、企業が避けて通れないのが「人材育成をどう設計するか」という問いです。
★経営層からの“施策要請型”プレッシャー
人材育成担当者に寄せられる経営層からの期待は、かつてのような「研修コストを削減せよ」
ではありません。今広がっているのは、「AIをテーマにした研修を実施せよ」「AIリテラシーを高める方針を示せ」という“施策要請型”のプレッシャーです。経営層もAIの重要性を理解しつつ、具体的にどう人材育成に落とし込むべきかまでは見えていません。そのため育成担当者に対し、「まずは研修で形にしてほしい」と求めるのです。
背景には、AIを前提にした事業モデルへの転換が進む中で「自社社員がAIを使いこなせる人材に育っているか」という不安があります。特にIT業界では競合他社が続々とAIを導入し、リスキリングに投資しています。その流れに取り残されれば事業継続が危ういという焦りが、育成への要請を強めています。
★経営層からの“施策要請型”プレッシャー
一方で、研修を受ける社員はAI時代特有の迷いを抱えています。
・「AIに聞けば答えが出るのに、研修を受ける意味はあるのか」
・「研修で学んだ知識はすぐにAIに置き換えられるのではないか」
・「業務でAIをどこまで使えばよいのか線引きが分からない」
・「AIに頼りすぎるとズルのように見えるが、使わないと遅れる気もする」
こうした声は一見受講者の戸惑いにすぎないように見えますが、実は企業にとって重要な問いです。
社員がAI活用に自信を持てず、迷い続ければ、組織全体の生産性向上も新規価値創出も進みません。
人材育成は、社員一人ひとりの迷いに答えを与える場であるべきです。
★世界の潮流と日本企業のギャップ
世界の大手IT企業はすでにAIを人材育成の基盤に組み込んでいます。マイクロソフト社はCopilotを通じて社員が日常的にAIを使いながらスキルを高められる仕組みを導入し、GoogleやAmazonは全社員向けにAIリスキリングプログラムを展開しています。米国の調査では、78%の企業が少なくとも1つの業務機能にAIを導入済みであり、71%の企業が生成AIを定常的に利用していると報告されています。
さらに従業員の94%が生成AIツールに慣れていると答え、約48%が「社内トレーニングがあればもっと使う」と意欲を示しているというデータもあります。つまり、米国ではAI教育がすでに「全社的な前提」として扱われているのです。
対照的に、日本企業の取り組みはまだ発展途上です。JUASの2025年調査によれば、言語生成AIを導入している企業は41.2%と前年より14ポイント増加し、確かに急速に広がっています。しかし、米国の水準と比べれば依然として差は大きいです。特に中小企業では導入率が低いという状況があります。
この数字が示すのは、海外ではAIが業務と人材育成の“当たり前”として組み込まれつつあるのに対し、日本は導入率が上がりつつも、依然として試験導入や一部の先進企業にとどまっているという現実です。
結果として、人材育成担当者は「やるべきなのは分かっているが、どう設計すればよいのか」という迷いを抱え、海外との差がさらなるプレッシャーを生んでいます。
★企業が取り組むべき問い
では、AI時代に企業はどのような人材育成を進めるべきでしょうか。
ここで重要なのは「AIをどう使うか」ではなく、「AI時代に求められる人材像をどう定義するか」です。
・AIを効率化ツールとして使える人材を育てるのか。
・AIを活用して新しい価値を創出できる人材を育てるのか。
・AIでは代替できない人間的能力(共感、倫理観、判断力)を伸ばすのか
この方向性を定めなければ、研修は単発のイベントに終わり、経営戦略と人材育成が乖離してしまいます。
AI時代の人材育成は「単なるスキル教育」ではなく、事業の存続と成長に直結する戦略課題になっているのです。
★戸惑いを成長の出発点に
AIの普及は、企業に「人をどう育てるのか」という根源的な問いを突きつけています。経営層は明確な答えを持っているわけではなく、育成担当者に「まずは形にしてほしい」と方針決定を委ねます。現場の社員は「AI時代に学ぶ意味」に迷い、担当者はその狭間で苦悩します。しかし、この戸惑いこそが新しい育成のスタートラインです。
AIは答えを提示する存在であると同時に、「人間にしかできない成長とは何か」を再考させる存在です。
企業にとっての人材育成は、もはや福利厚生ではなく、AI時代の競争力を決める基盤です。戸惑いを恐れず、問いに向き合い続けることこそが、AI時代に企業が果たすべき人材育成の責任なのです。